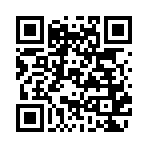2012年04月15日
おもいつき
桜が雨で散ってしまってさびしいな~と
桜もとめて ふと 行きたくなりました。
目指すは、いつもの富士山へ
朝、6時 ≪行くの?≫≪行く≫さっさと支度して、6時半出発!!
第二東名 新清水~新富士へ わずか20分 ・・・これはいい(*^_^*)
晴れたらこんな風に富士山も正面に!!

富士宮を登り・・朝霧は 名前のとおり霧につつまれて
今日は 富士山無理なのかしら?
ふと霧が晴れて・・・正面にこの富士山です

この富士山みたらね、これをみるために来たんだって思えたの。
続く、精進湖・・向こうに南アルプス 昨日の雨が冷たく雪になったようで

この時気温 3度・・・寒かった~
鳴沢を抜けて 富士吉田につく頃には、また霧が・・・
昨日の雨が多かったのでしょうね、太陽が照りだした8時には
いたるところから 水蒸気があがっていたから、
無理もないでしょう・・・・
ということで、とりあえず浅間公園へ
ちょうど桜まつりの奉納の神楽をみることができて


残念ながら、桜はまだまだでしたが・・。

続いて、富士桜のビューポイントへ一機に1000mあがりましたが、
もちろん桜つぼみかたく、残雪をみることとなりました。(笑)

暖かくなったら、また、あの場所へ 行こうと思ってますよ。
続いて、以前HULAを奉納した場所の方へと車を走らせ
以前より気になっていた場所に立ち寄ります。
国指定天然記念物≪船津胎内樹形≫この看板が気になっていたのです。


朝9時半 施設の方が丁寧に説明してくださり、
世界的にも貴重な地質学的資料なのだそうで、1000年以上まえに何度か噴火した富士山の溶岩流

洞穴は円形、溶岩流が途中木の幹をなぎ倒し取り込んだ形のまま固まってできたもの、溶岩樹型といいます。
船津樹型は延長18mの樹型(父の胎内)と2本の樹幹が連なった樹型(母の胎内)とを中心に総延長70mです。
中は溶岩鍾乳石が群生し、鉄分のため溶岩の一部が赤色をしており、樹型が肋骨状をしているので、
人間の体の内部に似ていることから「胎内」という名称で呼ばれてきました。
言い伝えによれば、昔から富士山岳信仰発祥の地として、古事記にも見られる木花咲姫命の分娩の洞窟穴といわれ、

江戸時代からの富士講では、富士山へ登るために一度この内部にはいり、生まれ変わって登る。というように
その頃の絵にも残っていました。

中は、電気がついているのではいれますが、ウサギ飛びのような姿勢で進む洞窟は、昨日の雨で
少し水がたまっていたり、上から滴る水に 不思議な感覚でした。



でもこんな経験できて、またひとつ富士山を知れたようです。(*^_^*)
戻ると、係の方が、このすぐそばにもあるので、と案内してくれて
森の中にある溶岩樹形をみる事ができました。

この溶岩樹形、ハワイにあるそうで、日本と貴重な資料のようです。
昨日の雨は冷たく、かなり下まで雪が降ったそうで、
例年 桜が咲くのですが、2週間ほど遅れているようです。
富士桜をあきらめて、帰路となるのですが、
富士宮についたのが 12時少しまえ
ディランさんが気になっていた、お蕎麦屋さんでおそばをいただき、


再び第二東名で帰宅。
すぐ、庭の倉庫の解体が今週末に決まったので
片付けとなったのです。
・・・それにしても、朝一番にみた富士山とすごく澄んだ空気をすって
充実した一日をすごしました。・・・・
おもいつきの行動は まだまだ続くでしょう・・・・・(笑)
桜もとめて ふと 行きたくなりました。
目指すは、いつもの富士山へ
朝、6時 ≪行くの?≫≪行く≫さっさと支度して、6時半出発!!
第二東名 新清水~新富士へ わずか20分 ・・・これはいい(*^_^*)
晴れたらこんな風に富士山も正面に!!

富士宮を登り・・朝霧は 名前のとおり霧につつまれて
今日は 富士山無理なのかしら?
ふと霧が晴れて・・・正面にこの富士山です
この富士山みたらね、これをみるために来たんだって思えたの。
続く、精進湖・・向こうに南アルプス 昨日の雨が冷たく雪になったようで
この時気温 3度・・・寒かった~
鳴沢を抜けて 富士吉田につく頃には、また霧が・・・
昨日の雨が多かったのでしょうね、太陽が照りだした8時には
いたるところから 水蒸気があがっていたから、
無理もないでしょう・・・・
ということで、とりあえず浅間公園へ
ちょうど桜まつりの奉納の神楽をみることができて
残念ながら、桜はまだまだでしたが・・。

続いて、富士桜のビューポイントへ一機に1000mあがりましたが、
もちろん桜つぼみかたく、残雪をみることとなりました。(笑)

暖かくなったら、また、あの場所へ 行こうと思ってますよ。
続いて、以前HULAを奉納した場所の方へと車を走らせ
以前より気になっていた場所に立ち寄ります。
国指定天然記念物≪船津胎内樹形≫この看板が気になっていたのです。

朝9時半 施設の方が丁寧に説明してくださり、
世界的にも貴重な地質学的資料なのだそうで、1000年以上まえに何度か噴火した富士山の溶岩流
洞穴は円形、溶岩流が途中木の幹をなぎ倒し取り込んだ形のまま固まってできたもの、溶岩樹型といいます。
船津樹型は延長18mの樹型(父の胎内)と2本の樹幹が連なった樹型(母の胎内)とを中心に総延長70mです。
中は溶岩鍾乳石が群生し、鉄分のため溶岩の一部が赤色をしており、樹型が肋骨状をしているので、
人間の体の内部に似ていることから「胎内」という名称で呼ばれてきました。
言い伝えによれば、昔から富士山岳信仰発祥の地として、古事記にも見られる木花咲姫命の分娩の洞窟穴といわれ、

江戸時代からの富士講では、富士山へ登るために一度この内部にはいり、生まれ変わって登る。というように
その頃の絵にも残っていました。

中は、電気がついているのではいれますが、ウサギ飛びのような姿勢で進む洞窟は、昨日の雨で
少し水がたまっていたり、上から滴る水に 不思議な感覚でした。

でもこんな経験できて、またひとつ富士山を知れたようです。(*^_^*)
戻ると、係の方が、このすぐそばにもあるので、と案内してくれて
森の中にある溶岩樹形をみる事ができました。

この溶岩樹形、ハワイにあるそうで、日本と貴重な資料のようです。
昨日の雨は冷たく、かなり下まで雪が降ったそうで、
例年 桜が咲くのですが、2週間ほど遅れているようです。
富士桜をあきらめて、帰路となるのですが、
富士宮についたのが 12時少しまえ
ディランさんが気になっていた、お蕎麦屋さんでおそばをいただき、
再び第二東名で帰宅。
すぐ、庭の倉庫の解体が今週末に決まったので
片付けとなったのです。
・・・それにしても、朝一番にみた富士山とすごく澄んだ空気をすって
充実した一日をすごしました。・・・・
おもいつきの行動は まだまだ続くでしょう・・・・・(笑)
Posted by kai at
22:50
│Comments(0)