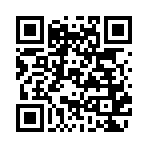2012年10月13日
舎人親王祭
江戸末期まで、清水区但沼字水神は親王原と呼ばれていたそうな・・。
舎人親王は 第四十代天武天皇の皇子で、第四十七代淳仁天皇の御父君にあたらせられる。
親王は、「日本書紀」を編纂された日本歴史上でもっとも著名かつ重要な御方。
親王は日本風土記編纂のため、諸国巡礼の旅にあがせられたが、信濃の国から駿河の国に
下る途次、この但沼の地で病にかかられてついに薨去したもうと伝えられる。
但沼の地に堀池秀次郎(天保5年死去)というひとがいた。
勤皇の精神極めて篤く、久能山東照宮の荘厳麗美大いに栄えるのに反し、舎人親王の御陵が
あまりにも衰微し貧弱なるを大いにふんがいして、自ら宮を建て、これを懇ろに祭っていたが、
たまたま徳川幕府の役人の忌避にふれるところとなり、
建物は壊滅され、但沼字山波止場河原にて焼却されてしまい
自らは清水区小河内字屋敷にながされたと伝えられる。
その当時、秀次郎の作った親王を像形した衣冠束帯の道祖神は、小河内坂本にあったが
この形式において日本唯一の珍しい貴重な作品で、今は御陵内に安置してある。
なお、秀次郎制作の舎人親王の御位牌は、但沼の臨済宗東壽院に現存している。
かく秀次郎は、菌のうの志が篤かったと共に、色々の才能に優れたひとであったから、
自ら笛太鼓などに楽器を作り、自らも演奏し村人にも教えて舎人親王の霊を慰め奉っていたと聞いている。
今に伝わる但沼の親王囃子は、おごそかな神寄せの舞の大拍子、五拍子、三拍子の神楽をはじめ、昇殿学、神田丸、
七丁目、馬鹿囃子、岡崎等の賑やかなお囃子で爾来 江戸末期から明治年間にいたり、親王さまの祭典や
氏神様のお祭りの際などにおおいに演奏され現在に至っている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日は、この地の舎人親王祭典です。
臨済宗東壽院では、舎人親王の御位牌が公開されています。
御陵も この日は 門が開かれていますよ。
親王囃子保存会のディランさん 朝からお祭りへ・・・・
・・江戸時代より続くお祭り そこには100有余年の歴史がある。・・・
舎人親王は 第四十代天武天皇の皇子で、第四十七代淳仁天皇の御父君にあたらせられる。
親王は、「日本書紀」を編纂された日本歴史上でもっとも著名かつ重要な御方。
親王は日本風土記編纂のため、諸国巡礼の旅にあがせられたが、信濃の国から駿河の国に
下る途次、この但沼の地で病にかかられてついに薨去したもうと伝えられる。
但沼の地に堀池秀次郎(天保5年死去)というひとがいた。
勤皇の精神極めて篤く、久能山東照宮の荘厳麗美大いに栄えるのに反し、舎人親王の御陵が
あまりにも衰微し貧弱なるを大いにふんがいして、自ら宮を建て、これを懇ろに祭っていたが、
たまたま徳川幕府の役人の忌避にふれるところとなり、
建物は壊滅され、但沼字山波止場河原にて焼却されてしまい
自らは清水区小河内字屋敷にながされたと伝えられる。
その当時、秀次郎の作った親王を像形した衣冠束帯の道祖神は、小河内坂本にあったが
この形式において日本唯一の珍しい貴重な作品で、今は御陵内に安置してある。
なお、秀次郎制作の舎人親王の御位牌は、但沼の臨済宗東壽院に現存している。
かく秀次郎は、菌のうの志が篤かったと共に、色々の才能に優れたひとであったから、
自ら笛太鼓などに楽器を作り、自らも演奏し村人にも教えて舎人親王の霊を慰め奉っていたと聞いている。
今に伝わる但沼の親王囃子は、おごそかな神寄せの舞の大拍子、五拍子、三拍子の神楽をはじめ、昇殿学、神田丸、
七丁目、馬鹿囃子、岡崎等の賑やかなお囃子で爾来 江戸末期から明治年間にいたり、親王さまの祭典や
氏神様のお祭りの際などにおおいに演奏され現在に至っている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今日は、この地の舎人親王祭典です。
臨済宗東壽院では、舎人親王の御位牌が公開されています。
御陵も この日は 門が開かれていますよ。
親王囃子保存会のディランさん 朝からお祭りへ・・・・
・・江戸時代より続くお祭り そこには100有余年の歴史がある。・・・
Posted by kai at 07:23│Comments(0)